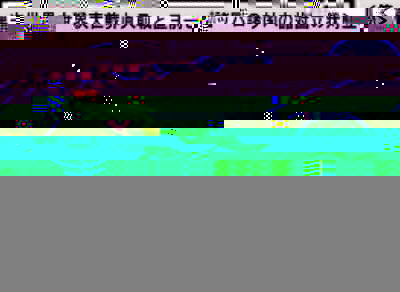| 岡井盛夫・日本人の歴史教室 |
|||||||||||||||||||||||||||
第一次世界大戦と日本 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
この文章は、NHK高校講座「日本史」(テレビ放送)の要約です。 第一次世界大戦は、日露戦争から10年後の1914年から始まった。この大戦には、ヨーロッパの荒廃とアメリカの台頭、ソ連の出現などの特徴があり、世界史の大転換期であった。 日本は、大戦を通じてアジア・太平洋にさらに膨張していった。つまり、大帝国主義へと拡大していった。 日露戦後の課題 ポーツマス講和条約(※)で日本は、遼東半島の旅順・大連の租借権や長春・旅順間の鉄道(満鉄)などの利権を獲得した。 ※1905年(明治38)9月、アメリカのポーツマスにおいて調印された日露戦争の講和条約。アメリカ大統領ルーズベルトの仲介によるもので、日本全権代表は小村寿太郎、ロシア全権代表はウィッテであった。 日露両国は1907年に協約を結び、満洲(中国北部)での互いの勢力範囲を確認しあった。アメリカは満鉄の日米共同経営を提案するなどして、満洲鉄道に割りこもうとして日本側と対立した。 日本では列強との緊張関係の中で、陸海軍が軍備の増強を求めた。大型戦艦の出現や中国での辛亥革命(1911年※)は、軍拡の主張に柏車をかけた。 ※中国で、清(しん)朝をたおし しかし、日本の経済・財政の行きどまりは深刻であった。日露戦争での内外債の元利払いのうえに、戦後の鉄道・治水・製鉄所拡張・電話事業などの公債が加わり、1913(大正2)年末の対外債務は一般会計歳入決算額の3倍近い20億円余となった。また、貿易は連年輸入超過を重ねていた。その一方で、営業税などの廃税を要求する運動も起っていた。
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ワシントン体制 第一次世界大戦を通して日本が中国や太平洋諸国に進出したことに対し、諸外国からはさまざまな不安や批判があった。そのため、アジア・太平洋地域で日本を含めた関係国が利害を調整し、行動に枠を設けるために開かれたのが、19211〜22年にかけてのワシントン会議であった。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
第一次世界大戦によって、日本はそれまでと一変して好景気となった。「大戦景気」であった。世界的な船の不足から、造船業や海運業が著しく伸びた。八幡製鉄所などを中心とした鉄鋼業や機械工業であった。それまで輸入に頼っていた化学、薬品工業なども発達し、工業国としての基礎が築かれた。 富山県東部を流れる黒部川では、大正時代に水力発電所が建設された。この時代に、機械の動力は、蒸気から電気に変わり、それが電源の開発、特に水力発電に拍車をかけた。
製糸業の発展と女工の労働環境
大戦景気によって、めざましい勢いで成長したのが、生糸を作る製糸業であった。日本各地で輸出に向けた生糸の生産が盛んになった。長野県の諏訪湖畔に立ち並ぶ製糸工場は、明治時代から製糸業が盛んな地域で、「諏訪千本」と言われるほど、工場の煙突が立ち並んでいた。ここでは、主に農村の貧しい女性たちが女工となり、製糸工場でまゆから糸をとった。労働は、1日14時間(※)にも及ぶものであった。女工の賃金は、とった糸の質や量によって決まった。100円以上を稼ぐ女工は、工場同士で取り合いになることもあった。しかし、過酷な労働で病気になって故郷に帰されたり、命を落とす女工たちも少なくなかった。 ※女工たちは、明朝5時15分に起床して、5時40分に就業した。途中食事休憩を挟みながら、夜は9時までの仕事であった。綿花から糸を作る紡績工場の女工たちには、深夜労働があった。彼女たちのことは、『女工哀史』(1925年・細井和喜蔵著)という本に描かれている。この本の最後のところで著者は、「女工問題こそは社会、労働、人道上あらゆる解放問題の最も先端に、中心に置いて考へられねばならぬ凡ての条件を具備して居る」、と書いてある。こうした女工たちが当時の日本経済を支えていた。 都市の近代文化 |
|||||||||||||||||||||||||||