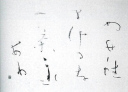| 岡井盛夫・11/01/16 |
|||||
小林一茶、特異な俳句と意外な性格 |
|||||
小林一茶(1763-1828年)は、松尾芭蕉(1644-1694年を敬愛した江戸時代の俳諧師です。その俳諧師が、この平成の時代であっても、非常にホピュラーな俳人です。(インターネットで検索すると、204の作品を読むことができる)。私に俳句を語る資格はありませんが、この夥しい俳句の中から、私選の代表作を取り上げます。
上の「親のない雀」は一茶52歳、「やせ蛙」は54歳、「雀の子」は57歳の句です。晩年の一茶が、童心を振り返り詠んだのでしょうか。彼の幼小の境遇(※)を考えれは、単なる童心ではないことが分かりますが、少なくも私は、童心そのものとして読んできました。 ※一茶は、信州信濃の北国街道柏原宿の農家の長男として生まれた。3歳の時に生母を失い、8歳で継母を迎える。継母に馴染めず、16歳で江戸に出て奉公をした。 大岡信著の『折々のうた 三六五日』に、次のような小林一茶の俳句が載っています。 春風や鼠のなめる隅田川 この俳句のことはエピローグでも取り上げますが、私の抱いていた「小林一茶の俳句」とは全く異質のものです。急に、小林一茶を調べたくなりました。やみくもに、井上ひさし著の『小林一茶』を読みました。この本は、いわば戯曲風「小林一茶伝」であります。一茶(本名弥太郎)が江戸に出て、俳諧師として独立するまでの前半生記です。この本によって、私は小林一茶の意外な人物像と俳風を見せつけられ、さらに「びっくり」しています。 井上ひさし著の『小林一茶』を読み進むと、私が持っていた小林一茶像がガタガタ崩れそうになりました。まるで別人のような一茶(弥太郎)と直面したからです。次は、その要約です。 (1)一茶は江戸に来た早々に、懸賞俳諧に巻き込まれた(詳細省略)。それをきっかけに、俳諧に強い関心を持つことになった。 (2)25歳の時、二六庵(小林竹阿)に師事して本格的に俳諧を学ぶ。 (3)30歳の3月、江戸を発ち東海道をのぼる。そして、36歳の年まで足かけ7年、京大阪・大和河内・四国九州などの各地を俳諧行脚した。(業俳というプロの生活に入った)。 ※松山城で、「御殿様主催の観月会」で絶賛された句 船頭よ小便無用浪の月 一茶はこの句を「真の滑稽です」と自画自賛している。 (4)39歳のとき再び帰省。病気の父を看病したが1ヶ月ほど後に死去、以後遺産相続の件で継母と12年間争う。一茶は再び江戸に戻り俳諧の宗匠を務めつつ遺産相続権を主張し続けた(※)。 ※晩年の俳句の作風からは想像もつかい執拗な自己主張。 先に、「ガタガタ崩れそうになった」と書いたのは、以上の経歴ではありません。戯曲風に書かれた井上ひさしの「小林一茶伝」が、私が抱いていた一茶像と全く違ったものであったからです。 (1)戯曲の主人公・弥太郎(小林一茶)は、猪首・赤ら顔・小肥・怒肩であった。 (2)一茶と交わった連中から、凶暴・短気・自信家・女に薄情などと酷評され、最初の奉公先が錠前屋であったことから、四百八十両の犯人扱いまでされている。 ※井上ひさしは、信濃毎日新聞社発行の『小林一茶全集』を何回となく通読している。「戯曲に登場する人物は、全て実在し、この戯曲の扱う事件はなにによらず史実である」と言い切っている。 江戸の一茶を語る時、一茶(弥太郎)・およね・竹里(ちくり・俳諧同人)の三角関係を抜きにすることはできません。戯曲では、およねに「俳諧が憎かったからではないが、弥太郎って男はあたしを捨てて俳諧を選んだ。竹里なんか大きらい。声を聞くだけで鳥肌がたつ。あたしの心はそういっている。ただ、からだはウンと頷いているんだょねぇ」と言わせています。次は、一茶が女を詠んだ珍しい句です。意外な意外な俳風です。 江戸川やあの美女恋せし時もあり うつくしや初雪のふる玉の肌
次の五句には、一茶の童心も弥太郎の「自信やつよがり」も見られません。もちろん、「女」も現れません。しかし、一茶本来の落ち着いた作風が感じられます。 春風や牛に引かれて善光寺 うつくしや障子の穴の天の川 これがまあ終のすみかか雪五尺 うまそうな雪がふうはりふうはりと 雪とけてくりくりしたる月夜かな 最後に、プロローグでとりあげた「春風や鼠のなめる隅田川」の補足です。次は、大岡信著の『折々のうた 三六五日』の解説の要点です。 -隅田川の川べりに並ぶ家から流れ出す残飯、残菓のたぐいをあさる鼠であろうか。しかしそのことはいわず、鼠が隅田川をなめていると大きくとらえたところに、江戸の春の情感が一気に溢れた。一茶は生涯に二万句前後を読んだという作家で、駄句も少なくないが、この句のような「奇々妙々」(江戸における一茶の後援者で、自らも俳人であった夏目成美の評)の作があるのはさすがだ。- 私がこの句を読んだ最初の印象は、素人の浅はかさでした。「隅田川をなめる鼠」は、残飯をあさるどぶ鼠ではありませんでした。目前に「隅田川をなめる鼠」が迫りくる思いでした。真にスケールの大きい「写生」でした。だから、決して「奇々妙々」でもありません。 なお、解説に補足を付ける気持ちはありませんが、俳諧師であった弥太郎時代の一茶は、即興の連句や「同音読みや廻文」(俳諧の形式)などに加わりました。駄句が多いのは当然のことです。さらに、弥太郎の俳諧と晩年一茶の俳句を見比べると、俳句の作風において著しい飛躍があることを特筆しなければなりません。その一茶の人格は、父親の遺産相続について、一歩も譲らないほどの、かたくなな性格の人でした。 【追記】 ①小林一茶は、文政10年(1827年7月24日)、信濃柏原宿を襲う大火に遭い、母屋を失い、焼け残った土蔵で生活をするようになった。そしてその年の11月19日、その土蔵の中で65歳の生涯を閉じた(Wikipedia)。 ②童門冬二著『小林一茶』は、晩年の一茶の性格について詳しく記述している。これまた、意外な性格である。躁鬱性、人におだてられるとすぐその気になる。批判されると絶望感に襲われるが長続きはしない。自己嫌、勝手で協調性や妥協性が乏しい。芸術家肌、サービス精神旺盛などなど。
|
|||||